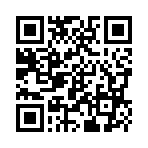2007年05月05日
演奏会の裏話 9.儀式
演奏会で曲の前に行われるチューニング、、
一つの儀式のようなものですが、通常A(ラ)を442HZに
合わせます。
以前は440HZだったようですが、今では大抵442が多いのではないでしょうか?
オーボエが基の音を出し、それをコンサートマスターが受け取り、
各パートに渡します。
ピアノコンチェルトの場合、ピアノの調律に合わせますので、以前は440がほとんどでした。
今では、ピアノも442でのチューニングとか出来るので、普通にチューニングができます。
一つの儀式のようなものですが、通常A(ラ)を442HZに
合わせます。
以前は440HZだったようですが、今では大抵442が多いのではないでしょうか?
オーボエが基の音を出し、それをコンサートマスターが受け取り、
各パートに渡します。
ピアノコンチェルトの場合、ピアノの調律に合わせますので、以前は440がほとんどでした。
今では、ピアノも442でのチューニングとか出来るので、普通にチューニングができます。
そうやって音を合わせるのですが、いざ演奏が始まるといろいろ厄介なことが起こります。
弦楽器の場合、ステージ上でライトを浴び、温度が上がると、音程は下がってきます。
逆に、管楽器は音程が上がってきますので、演奏中で、金管とか、管の長さを微調整して、
音をそろえます。
演奏中ホルンとか、見ていると面白いかもしれません。
ティンパニーも、結構スリリングに音あわせてます。
今の弦、ドミナントとかエヴァピラッツィとかあまり狂わないのですが、
ガット弦は結構微妙でした。
なので開放弦を奏くのが、難しくなっていくことがあり、指使いを変えることもあります。
ですので、長い曲など(やたら暑い時とか)楽章の合間に、チューニングを行うこともあります。
実は演奏前ステージ袖に集合し、で、チューニングメーターで各人基音に調整してます。
なのでステージ上で音を合わせることは、あまりありません。
管楽器など音を合わせるというより、ステージの雰囲気を演奏者が感じ取ったり、
楽器を慣れさせたりする意味合いが強いといえましょう。
弦楽器の場合、ステージ上でライトを浴び、温度が上がると、音程は下がってきます。
逆に、管楽器は音程が上がってきますので、演奏中で、金管とか、管の長さを微調整して、
音をそろえます。
演奏中ホルンとか、見ていると面白いかもしれません。
ティンパニーも、結構スリリングに音あわせてます。
今の弦、ドミナントとかエヴァピラッツィとかあまり狂わないのですが、
ガット弦は結構微妙でした。
なので開放弦を奏くのが、難しくなっていくことがあり、指使いを変えることもあります。
ですので、長い曲など(やたら暑い時とか)楽章の合間に、チューニングを行うこともあります。
実は演奏前ステージ袖に集合し、で、チューニングメーターで各人基音に調整してます。
なのでステージ上で音を合わせることは、あまりありません。
管楽器など音を合わせるというより、ステージの雰囲気を演奏者が感じ取ったり、
楽器を慣れさせたりする意味合いが強いといえましょう。
Posted by あきひろ佐藤 at 11:09│Comments(8)
│演奏会の裏話
この記事へのコメント
あ様
最近はクラシックはとんとご無沙汰ですが、演奏が始まる前に
小さな音でチューニング?なさる時があり、指揮者が現れる前の
緊張感と期待が増し、あの瞬間がとても好きです。
一度、とても疲れていて心地よい調べについうとうとしていたらしく、
ティンパニーの音に飛び上がって(本当に)今でも忘れらえない恥かしい思い出です。
それ以後音楽会に行く時は事前に聴いて、どの楽章のどの辺でティンパニーが・・・と、調べたこともありました(笑)
やはり私は椅子に寝転んで聴いている方が似合いますね。
時々菜箸を指揮棒代わりに振り回したり・・・失礼致しました!(笑)
最近はクラシックはとんとご無沙汰ですが、演奏が始まる前に
小さな音でチューニング?なさる時があり、指揮者が現れる前の
緊張感と期待が増し、あの瞬間がとても好きです。
一度、とても疲れていて心地よい調べについうとうとしていたらしく、
ティンパニーの音に飛び上がって(本当に)今でも忘れらえない恥かしい思い出です。
それ以後音楽会に行く時は事前に聴いて、どの楽章のどの辺でティンパニーが・・・と、調べたこともありました(笑)
やはり私は椅子に寝転んで聴いている方が似合いますね。
時々菜箸を指揮棒代わりに振り回したり・・・失礼致しました!(笑)
Posted by クッキーママ at 2007年05月05日 22:24
あ 様
本番前のチューニングは、音と言うより、心気のチューニングですね。
心をそろえる儀式、とでも申しましょうか。
(そういえば、先日の聖徳の吹奏楽、最初に全員ユニゾンでの音階をやりました)
古楽では、弦は生ガットで、しかも開放弦を多用するし、ビブラートはほとんどかけないし、いつも感心します。だいいち、Aは440などではなく、415とか、昔のピッチにあわせます。(だから管は、時代ごとにいろんなピッチの楽器をそろえておく必要があります。ピッチを調整することは不可能なので)
ちなみに、ハーディ・ガーディという楽器を演奏したことがありますが、これに使う弦として最適だったのが、なんとバドミントンのガットでした。そう、弦楽器の弦もバドミントンやテニスのガットも、むかしむかしは同じようなものでしたから。
冬野
本番前のチューニングは、音と言うより、心気のチューニングですね。
心をそろえる儀式、とでも申しましょうか。
(そういえば、先日の聖徳の吹奏楽、最初に全員ユニゾンでの音階をやりました)
古楽では、弦は生ガットで、しかも開放弦を多用するし、ビブラートはほとんどかけないし、いつも感心します。だいいち、Aは440などではなく、415とか、昔のピッチにあわせます。(だから管は、時代ごとにいろんなピッチの楽器をそろえておく必要があります。ピッチを調整することは不可能なので)
ちなみに、ハーディ・ガーディという楽器を演奏したことがありますが、これに使う弦として最適だったのが、なんとバドミントンのガットでした。そう、弦楽器の弦もバドミントンやテニスのガットも、むかしむかしは同じようなものでしたから。
冬野
Posted by 冬野由記 at 2007年05月05日 23:09
クッキーママ 様
ご来場ありがとうございます。
実は、あれが「チューニング」というプログラムに載っていない曲なのです。
(冗談です)
ティンパニーでビックリする曲といえば、ハイドンの「驚愕」かも
知れませんね。
私は、お金払って曲を聴いているのですから、周りに迷惑にならなうように、
爆睡することがあります。気持ち良いですよ。。。
危なかしい演奏の時は、逆にスリリングで寝てもいられませんが、
やっぱ生音は、どんなステレオより良いでしょう。
どうぞお気楽に演奏会へ行かれては??
ご来場ありがとうございます。
実は、あれが「チューニング」というプログラムに載っていない曲なのです。
(冗談です)
ティンパニーでビックリする曲といえば、ハイドンの「驚愕」かも
知れませんね。
私は、お金払って曲を聴いているのですから、周りに迷惑にならなうように、
爆睡することがあります。気持ち良いですよ。。。
危なかしい演奏の時は、逆にスリリングで寝てもいられませんが、
やっぱ生音は、どんなステレオより良いでしょう。
どうぞお気楽に演奏会へ行かれては??
Posted by あ at 2007年05月06日 00:29
冬野 様
ご来場ありがとうございます。
そうですね、音をステージで出しておかないと、やっぱ落ち着かないもので
気持ちを整える意味で、気心のチューニンング、ご指摘のとおりです。
N響が昨年アーノンクールで、ノンビブラートをやったのには驚愕でした。
本人曰く古楽の様式をあえてやるのは、かび臭い音楽を、
現代に再現させようとするものでは無く、もっと熱いものだと言いきった
ところに潔いものを感じました。
モーツァルトも絶対音がなかったくらい、当時のAはいろいろあったそうで、
ピッチごとに楽器をそろえる必要はあるのでしょうね。
さすがに415とかで演奏したことはありませんが、、、、
ほんとに昔はガットかスチールしか、弦がなくて、、、
C線、無理して買って(9000円)、一週間でお釈迦ってこともありました。
まあ、そのガットと言ったって、アルミが巻いてあるんですが、
羊の腸とかよじってた時代、どうだったんでしょうね?
ハーディーガーディー、存じ上げません。
調べてみます。
ご来場ありがとうございます。
そうですね、音をステージで出しておかないと、やっぱ落ち着かないもので
気持ちを整える意味で、気心のチューニンング、ご指摘のとおりです。
N響が昨年アーノンクールで、ノンビブラートをやったのには驚愕でした。
本人曰く古楽の様式をあえてやるのは、かび臭い音楽を、
現代に再現させようとするものでは無く、もっと熱いものだと言いきった
ところに潔いものを感じました。
モーツァルトも絶対音がなかったくらい、当時のAはいろいろあったそうで、
ピッチごとに楽器をそろえる必要はあるのでしょうね。
さすがに415とかで演奏したことはありませんが、、、、
ほんとに昔はガットかスチールしか、弦がなくて、、、
C線、無理して買って(9000円)、一週間でお釈迦ってこともありました。
まあ、そのガットと言ったって、アルミが巻いてあるんですが、
羊の腸とかよじってた時代、どうだったんでしょうね?
ハーディーガーディー、存じ上げません。
調べてみます。
Posted by あ at 2007年05月06日 00:43
あきひろ 様
おきな草 から
絶対音感は素より、相対音感をも持っていない私には、2KHzの相違などは、峻別できません。ただただ、感心し、演奏家を畏敬するのみです。
昔、ピタゴラスの平均律とかで、「ラ」音は、440KHzに決まっているのだが、この周波数だと、全体が澄んだ音になるとともに、全体が、僅かに濁るのだと聞いたことがあります。
最近の、リスナーの耳は肥えているのでしょうね。私も、耳無法市にならぬよう、時間の許す限りオタマジャクシを、聴き、触ってみたいと思います。
ありがとうございました。
おきな草 から
絶対音感は素より、相対音感をも持っていない私には、2KHzの相違などは、峻別できません。ただただ、感心し、演奏家を畏敬するのみです。
昔、ピタゴラスの平均律とかで、「ラ」音は、440KHzに決まっているのだが、この周波数だと、全体が澄んだ音になるとともに、全体が、僅かに濁るのだと聞いたことがあります。
最近の、リスナーの耳は肥えているのでしょうね。私も、耳無法市にならぬよう、時間の許す限りオタマジャクシを、聴き、触ってみたいと思います。
ありがとうございました。
Posted by おきな草 at 2007年05月06日 09:25
おきな草 様
ご来場ありがとうございます。
私には絶対音はありません。じゃあ相対音感があるか?といえば、
そこそこでしょうか、、、、、
チューニングメーターで、1HZ,2HZの違いを聴くことができますが、
変わったかな?ぐらいで、全体への影響、どうなんでしょう?
442で音あわせをした方が、全体的に明るい感じになるみたいです。
でも、ぶっちゃけた話、演奏が始まったら、音程は自ら探すので、
気休めなのかもしれません。
音楽は、心を和ませてくれたり、懐かしさを醸し出してくれたりで、
素晴らしいものです。
どうぞお気軽にお楽しみいただければと思います。
ご来場ありがとうございます。
私には絶対音はありません。じゃあ相対音感があるか?といえば、
そこそこでしょうか、、、、、
チューニングメーターで、1HZ,2HZの違いを聴くことができますが、
変わったかな?ぐらいで、全体への影響、どうなんでしょう?
442で音あわせをした方が、全体的に明るい感じになるみたいです。
でも、ぶっちゃけた話、演奏が始まったら、音程は自ら探すので、
気休めなのかもしれません。
音楽は、心を和ませてくれたり、懐かしさを醸し出してくれたりで、
素晴らしいものです。
どうぞお気軽にお楽しみいただければと思います。
Posted by あ at 2007年05月06日 10:43
あきひろ 様
おきな草 から
先ほどのコメントで、周波数の単位を間違えました。
KHzではなく、単に、Hzと読み替えて下さい。半可通で申し訳ありません。
おきな草 から
先ほどのコメントで、周波数の単位を間違えました。
KHzではなく、単に、Hzと読み替えて下さい。半可通で申し訳ありません。
Posted by おきな草 at 2007年05月06日 12:56
おきな草 様
ああ、そうですですね。
KHzでチューニングしたら、弦すぐ切れちゃいます。
あの後思い出したのですが、金属板に鉄粉を敷いて、438Hzから振動を、
加え、439、そして440になったとたん、鉄粉が綺麗な模様になる画像を
見たことがありました。
カラヤンなど、絶対音のある人に言わせれば、曲の最後あたりは、
444Hzになっていたりで、気持ち悪いとか、、、、、、
やはり、相対音で十分かもしれません。
ああ、そうですですね。
KHzでチューニングしたら、弦すぐ切れちゃいます。
あの後思い出したのですが、金属板に鉄粉を敷いて、438Hzから振動を、
加え、439、そして440になったとたん、鉄粉が綺麗な模様になる画像を
見たことがありました。
カラヤンなど、絶対音のある人に言わせれば、曲の最後あたりは、
444Hzになっていたりで、気持ち悪いとか、、、、、、
やはり、相対音で十分かもしれません。
Posted by あ at 2007年05月06日 16:16
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。